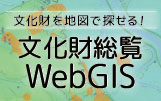総覧抄録ID : 55972
要約 : [市原条里制遺跡(藤井 要約]\n市原条里制遺跡は市原台地の北西部に広がる標高4m〜5mの沖積低地上に立地する。藤井地区・五井本納線橋脚部は遺構の検出はない。縄文時代は中期から後期の土器・土器片錘、石器(石鏃・磨石・敲石・石皿)が出土した。古代以降の土器・陶磁器をみると、土師器、土師質土器、瓦質鍋、常滑、山茶碗、青磁、白磁、染付がある。そのほかに、煙管、土師器片転用紡錐車、新寛永銭が出土した。 \n[市原条里制遺跡(郡本 要約]\n市原条里制遺跡は市原台地の北西部に広がる標高4m〜5mの沖積低地上に立地する。郡本地区は畦畔・溝・道路跡が検出されたが、古代末から近世にわたるものである。古代以降の土器・陶磁器をみると、土師器、須恵器、土師質土器、瓦質鍋、瀬戸・美濃、常滑、渥美、山茶碗、青磁、白磁、染付がある。そのほかに、曲物等の木製品、瓦(丸瓦・平瓦)、銭貨(中世銭・寛永銭)が出土した。 \n[市原条里制遺跡(市原 要約]\n市原条里制遺跡は市原台地の北西部に広がる標高4m〜5mの沖積低地上に立地する。市原地区の縄文時代は、中期から後期の土器・土器片錘が出土した。弥生時代は、遺構はないが中期宮ノ台式土器が出土した。奈良・平安時代は古道跡が検出された。古代東海道の支線級の官道であり、重要な成果である。道路幅は5.5m前後で、両側に側溝をもつ。遺物は「□□米五斗」と書かれた付札木簡が出土したことも注目される。条里遺構の調査は、地籍図などに基づいて想定復元した一町方格の大畦畔を中心に行い、古代・中世前半・中世後半・近世の水田4面とそれに伴う畦畔・水路を検出した。中世・近世の水田は、ほぼ現条里と同様な形態で、坪内地割りは長地型を基本とする。古代の大畦畔からは多数の木杭・田下駄が出土した。古代は湿田的、中世以降は乾田的性格である。古代以降の土器・陶磁器をみると、土師質土器、羽釜、瓦質鍋、瀬戸・美濃、常滑、渥美、山茶碗、青磁、白磁、染付がある。そのほかに各種の瓦、鉄製品(鉄鏃・火打金など)、銭貨(中世銭・寛永銭)が出土した。 \n[市原条里制遺跡(菊間 要約]\n市原条里制遺跡は市原台地の北西部に広がる標高4m〜5mの沖積低地上に立地する。菊間地区は畦畔・溝が検出されたが、古代末から近世にわたるものである。弥生時代中期、古墳時代前期・後期の土器が出土した。古代以降の土器・陶磁器をみると、土師質土器、羽釜、瓦質鍋、瀬戸・美濃、常滑、渥美、山茶碗、青磁、白磁、染付がある。木製品は直柄鍬・又鍬・田下駄などが出土した。そのほかに瓦(軒丸瓦・丸瓦・平瓦)、甎、銭貨(中世銭・寛永銭)がある。 \n[市原条里制遺跡(徳万地区) 要約]\n市原条里制遺跡は市原台地の北西部に広がる標高4m〜5mの沖積低地上に立地する。徳万地区では遺構はみられない。旧石器時代は石刃が1点出土した。縄文時代は、早期から中期の土器・土器片錘が出土した。古代以降の土器・陶磁器をみると、瀬戸・美濃、常滑、山茶碗、青磁、白磁がある。そのほかに、木製品(田下駄・曲物)、瓦(丸瓦・平瓦)、銭貨(中世銭・寛永銭)が出土した。 \n[市原条里制遺跡(並木地区) 要約]\n市原条里制遺跡は市原台地の北西部に広がる標高4m〜5mの沖積低地上に立地する。並木地区の縄文時代は、早期から前期の土器が出土し、一部は貝塚の可能性がある。また一定量の土器片錘がみられる。弥生時代は北区で中期の小区画水田が170区画以上・水路2条が検出され、水路からは土器・木製品が大量に出土した。南区では古墳時代後期の小区画水田が85区画以上・水路3条が検出された。一部の畦畔には補強のため、粗朶を主体とした芯材が埋め込まれている。並木地区および実信地区の調査により、大規模な水田経営が行われたことが判明した。木製品の種類には、エブリ・田下駄・曲物・大足・木鏃(細身鏃)・剣形品がある。古代以降の土器・陶磁器をみると、土師質土器、羽釜、瓦質鍋、瀬戸・美濃、常滑、山茶碗、青磁、白磁、染付がある。そのほかに、瓦(丸瓦・平瓦)、金属製品(刀子・煙管)、土製品(管状土錘・土玉・羽口)、銭貨(五銖銭・中世銭・寛永銭)が出土した。 \n[市原条里制遺跡(実信地区) 要約]\n市原条里制遺跡は市原台地の北西部に広がる標高4m〜5mの沖積低地上に立地する。実信地区の縄文時代は中期後半を中心とする貝塚があり、一定量の土器片錘も出土した。貝塚は加曽利E2式新段階から始まり、晩期終末の前浦式期まで続く。主体は加曽利E2式からE3式期である。中期後半の実信貝塚は周囲に集落がないことから、集落から距離的に離れた漁労の場とみられる。後期前半以降は近くの台地に菊間手永貝塚の集落があり、実信貝塚と関わる遺跡であろう。弥生時代は中期宮ノ台式土器を含む自然流路・堤状遺構・畦畔が見つかったが、水田遺構は検出されない。自然流路からは土器・木製品が大量に出土し、木製品には樹皮を巻き付けた弓やタモ枠などが出土した。古代以降の土器・陶磁器をみると、土師質土器、羽釜、瓦質鍋、瀬戸・美濃、常滑、渥美、山茶碗、青磁、白磁、染付がある。そのほかに、瓦(軒丸瓦・軒平瓦・丸瓦・平瓦)、金属製品(刀子・火打金・銅製鍔・煙管)、土製品(管状土錘・紡錐車・円盤・羽口・土玉・勾玉)、石製品(勾玉・丸玉・紡錐車)、ガラス丸玉、銭貨(承和昌寳・中世銭・寛永銭)が出土した。 \n[市原条里制遺跡(村田 要約]\n市原条里制遺跡は市原台地の北西部に広がる標高4m〜5mの沖積低地上に立地する。村田川橋脚部は溝状遺構が4〜6条と水田2区画が検出された。時期は中世以降と思われる。古代以降の土器・陶磁器をみると、土師器杯、土師質土器、瀬戸・美濃、志野、常滑、白磁がある。そのほかに、銭貨(中世銭・寛永銭)が出土した。 \n
遺跡名 : 市原条里制遺跡(徳万地区)
都道府県 : 千葉県
遺跡所在地 : 千葉県市原市菊間字徳万30ほか
市町村コード : 12219
北緯(世界測地系) : 35.5305
東経(世界測地系) : 140.1248
主な時代 : 縄文
時代・遺跡種別 : 散布地
主な遺構|主な遺構 :
主な遺物|主な遺物 : 縄文土器|木製品
総覧URL : https://sitereports.nabunken.go.jp/31489
特記事項 : 種別:包蔵地\n\n遺跡名かな:いちはらじょうりせいいせき(とくまんちく)