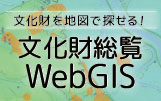総覧抄録ID : 43674
要約 : 6世紀後葉に集落が始まる。隣に同じ時期の判官塚古墳が存在し、その首長のもと開発がなされる。7世紀前葉に竪穴住居の数が急増し、8世紀から小規模になる。遺跡のある都賀郡では、奈良時代には散居集落が多く、管下の集落の傾向に沿う。国府や国分寺周辺への集住化に対した散村化といえる。特殊な遺物としては、黒川に近いため編物石が多く出土し、漆付着土器・朱付着土器・製塩土器などもある。遺構では、カマドの煙道が細長い点が特徴である。 中世では、鎌倉時代から室町・戦国期までの区画溝が確認され、周辺の地割に沿っていた。その区画は、県内では下古館遺跡に類似するものと推測される。中世瓦が一定数出土した。 \n
遺跡名 : 青龍渕遺跡
都道府県 : 栃木県
遺跡所在地 : 栃木県鹿沼市北赤塚町289他
市町村コード : 9205
北緯(世界測地系) : 36.479974
東経(世界測地系) : 139.765683
主な時代 : 不明|古墳|飛鳥白鳳|奈良|平安|中世(細分不明)
時代・遺跡種別 : 集落
主な遺構|主な遺構 : 掘立柱建物跡1棟|竪穴住居跡143軒|溝跡7条|井戸跡1基|地下式坑1基|土坑(近現代を含む)146基
主な遺物|主な遺物 : 土師器|須恵器|鉄製品|編物石|朱付着土器など|かわらけ|瀬戸|常滑|瓦など
総覧URL : https://sitereports.nabunken.go.jp/24933
特記事項 : |古墳時代後期〜平安時代の集落|鎌倉時代以降の区画溝