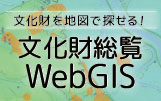総覧抄録ID : 36919
要約 : 伊坂城跡 : 朝日丘陵の端部に位置する戦国時代の城館である。第6次調査は、本丸に相当する曲輪1の北半分、二の丸に相当する曲輪2のほぼ全面を中心に調査を行った。調査の結果、曲輪1において礎石を有する櫓門1棟、掘立柱建物4棟以上、井戸1基、曲輪3において石つぶて遺構1基、曲輪2において門1基、カマドの可能性を持つ土坑1基などを確認した。曲輪1、曲輪2の北側は斜面を急峻に削ることで守りを固めており、斜面の下端には平坦面が認められた。この平坦面(曲輪11~16)から麓へ斜面が続くが、この斜面については自然地形と判断できた。また、曲輪6、8、9の西端では自然地形の谷が南北方向に伸びていた。これらから第6次調査区の北側、西側には遺跡範囲が広がらないことが判明した。なお、東側に隣接ぢて第7次調査を実施した。出土した土器から、伊坂城は15世紀末~16世紀後半に築城され、16世紀後半まで城として機能していたことが考えられる。\n北山C遺跡 : 第7次調査は、今年度調査を行った第6次調査の東側に位置し、第6次調査とは堀切により隔てられている。調査の結果、西区では第6次調査に隣接する平坦地において、掘立柱建物3棟・土坑・溝・柱穴を検出した。平坦地の北側には犬走り状の平坦地があり、第6次調査と第7次調査下段の平坦地をつなぐ通路として利用されたと考えられる。また、西区中央部では土壇状の高まりがあり、盛土により造成されていることが確認された。中区では、下層土坑と考えられる壁面が被熱により、硬化・赤変し、多量の炭化材を含む土坑を2基検出した。うち1基からは骨片が出土している。また、中央部には溝で囲まれた土壇状の高まりが確認されたが不明である。西区・中区の斜面部および東区では部分的に平坦地を確認したものの明確な遺構は確認できなかった。\n北山A遺跡 : 桑名市南部を流れる員弁川の南岸、四日市市にかけて広がる丘陵上に位置する。今回の調査区は、平成25年度の第4次調査区の北端、東端と隣接する。調査の結果、新たに21基の方墳と1基の円墳を確認した。墳丘は削平され、大半の古墳は周溝を残すのみであったが、1基で主体部が残存しているのを確認し、そこから刀子が出土した。他の古墳においても周溝埋土から5世紀代の須恵器と土師器、また1基から埴輪が出土した。また、古墳時代の土壙墓が16基確認され、鉄製品および砥石、勾玉が出土した。\n中野山遺跡 : 員弁川と朝明川に挟まれた丘陵上に立地している。今回の第6次調査では、土壙、ピットなどとともに、飛鳥時代から奈良時代にかけての竪穴住居2棟、掘立柱建物1棟が確認された。昨年度までに行われた第2次・第3次・第5次調査の結果と合わせると、北山A遺跡に営まれた飛鳥時代から奈良時代にかけての集落には、掘立柱建物が集中して建てられた地区があることが明らかになった。また中野山遺跡の調査結果とも合わせると、集落は、中野山遺跡の東部の集落と一連であると考えられる。\n北山城跡 居林遺跡 : 第13次発掘調査では、縄文時代の土壙6基、古墳時代後期から飛鳥時代の竪穴住居15棟・掘立柱建物16棟・大型土坑7基、中世の墓などを確認した。遺構は、調査区東部に集中している。西部には見られないことから、中野山遺跡における集落の西端部と考えられる。縄文時代の袋状土坑を1基確認した。隣接する第9次・第12次調査区でも計6基確認しているが、類例の少ない遺構である。中から後期初頭の土器が出土した。弥生時代の竪穴住居などは見られないものの、ピットから弥生土器片が数点出土した。古墳時代後期から飛鳥時代竪穴住居や掘立柱建物の中には、方向を同じ西隣接するものが数棟見られた。出土した須恵器や土師器からも同時代の遺構と考えられ、計画的に建てられたことが想定された。\n小牧南遺跡 : 3箇所の調査坑を設定したが、いずれの調査坑においても遺構・遺物ともに確認されなかった。(一次調査・174㎡)\n椋ノ木遺跡 : 調査坑を4本(T1~T4:延長87m)設定して遺構・遺物の有無についての調査を行った。遺物はT2から須恵器片・山茶椀片が1点出土したが、大半は近現代の陶器片である。また、いずれの調査坑でも、攪乱と近現代の溝(落ち込み?)を確認したにとどまり、明確な遺構は確認されなかった。(一次調査・174㎡)調査坑を4本(T5~T8)設定して遺構・遺物の有無についての調査を行った。結果、T5・T6では造成土が広範囲に入っているのを確認し、T7・T8では近現代の耕作に伴うと思われる溝及び地表構造物の埋設物に伴う攪乱を認めた。いずれの調査坑でも遺構・遺物は確認されなかった。(一次調査・186㎡)\n高ノ瀬遺跡 : 新名神高速道路建設に伴う集落排水管移設工事が行われるにあたって工事立会を行った。総延長54m、幅1mの範囲を調査したが、遺構、遺物ともに確認されなかった。(一次調査54㎡)調査坑を8本(T22~T29)設定し行ったが、安定した遺構検出面は確認されず、遺構の検出されなかった。遺物は、小片が少量出土したが、いずれも攪乱穴からである。(一次調査・715㎡)\n小社遺跡 : 鍋川北岸に位置する。現況は標高153~155mの北西から南東に向かって傾斜する扇状地に立地し、現況は畑地である。調査の結果、A地区では近世以降と考えられる掘立柱建物1棟・溝・土坑・柱穴等を確認した。出土遺物は土師器(皿・羽釜・茶釜・焙烙)、瀬戸美濃産陶器(椀・皿・擂鉢)、常滑産陶器(甕・鉢)、青磁等の土器の他、五輪塔(火輪)・石臼等が出土している。\n\n\n
遺跡名 : 北山城跡 居林遺跡
都道府県 : 三重県
遺跡所在地 : 四日市市北山町
市町村コード : 24202
北緯(世界測地系) : 35.047222
東経(世界測地系) : 136.581388
主な時代 : 弥生|古墳|奈良|平安|中世(細分不明)
時代・遺跡種別 : 集落
主な遺構|主な遺構 : 竪穴住居|掘立柱建物|土坑|溝|ピット
主な遺物|主な遺物 : 弥生土器|土師器|須恵器|石器
総覧URL : https://sitereports.nabunken.go.jp/21167
特記事項 :