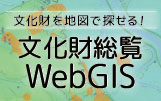総覧抄録ID : 27818
要約 : 浅間山麓の佐久平北部では、厚く堆積した軽石流により形成された台地を河川が浸食して深い谷となった「田切り地形」と呼ばれる独特の地形を形成する。本書掲載の周防畑遺跡群はこうした田切の一つである濁川の田切谷に面した台地が途切れた先の緩傾斜地に立地する。周防畑遺跡群では、弥生時代の集落と墓跡、奈良~平安時代の集落を検出した。弥生時代中期の集落は小規模で、竪穴住居跡3件が南部の5区で検出している。弥生時代後期になると、5区の集落が拡大し、新たに北部の2・3区にも集落が形成されるとともに、5区の集落の南西部に隣接して墓域が形成される。この墓域内の円形周溝墓の周溝縁から国内最大級のヒスイ製勾玉、土坑墓の一つから三連の銅釧が出土し、2区の土器棺墓からは滑石製管玉6個とガラス小玉23個が出土している。古代の集落は北部の2・3区にみられる。薬壺と思われる須恵器短頸壺や土師器鉄鉢形土器が竪穴住居跡から出土し、遺構外では須恵器獣脚風字硯や川原寺式軒丸瓦が出土するが、これ以外に硯と帯金具や皇朝十二銭の出土はなく、灰釉陶器や墨書土器の出土も少ない。近辺にあったと考えられる佐久郡衙に関連するとしても下のクラス、郡雑人等の集落と思われる。その中で、10世紀後半に成立した2区北部の掘立柱建物群の地区では、墨書を含む灰釉陶器と灯明具を多数使用する祭祀を行っており、有力者の屋敷地と思われる。
遺跡名 : 周防畑遺跡群
都道府県 : 長野県
遺跡所在地 : 長野県佐久市大字長土呂字大豆田1705
市町村コード : 20217
北緯(世界測地系) : 36.2834
東経(世界測地系) : 138.4541
主な時代 : 縄文|弥生|古代(細分不明)
時代・遺跡種別 : 集落
主な遺構|主な遺構 : 陥し穴|竪穴住居跡64|円形周溝墓|方形周溝墓18|土坑墓5|土器棺墓4|竪穴住居跡41|掘立林建物跡13
主な遺物|主な遺物 : 土器|打製石斧|磨製石斧|磨製石鏃|勾玉|管玉|ガラス小玉|銅釧|土師器|須恵器|黒色土器|灰釉陶器|緑釉陶器|青磁|砥石|刀子|鉄製紡錘車|銭貨|墨書土器|風字硯|軒丸瓦
総覧URL : https://sitereports.nabunken.go.jp/351
特記事項 : |土坑墓から三連銅釧出土。円形周溝墓の周溝の縁からヒスイ製勾玉出土。土器棺墓の中から管玉6とガラス小玉23が出土。|奈良時代の竪穴住居跡から須恵器短頸壺や土師器鉄鉢形土器、平安時代の土坑から墨書されたものを含む灰釉陶器がまとまって出土。遺構外で須恵器獣脚風字硯や川原寺式軒丸瓦が出土。\n