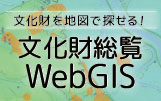総覧抄録ID : 147143
要約 : [中山城跡第5・6次 要約]\n中山城は南北に長い城で、平坦な郭が連なった連郭式の山城である。発掘調査により、自然の地形を改変して郭が造られたこと、郭の周囲に堀切や切岸(急な斜面)が造られたこと、平坦な郭には簡単な建物や柵が作られていたこと、城が一度造り替えられ郭が広げられたことがわかった。現段階では、16世紀前半に築造され、16世紀後半に改造されたものと判断される \n\n[井脇城跡 要約]\n井脇城跡中心部の南東側に設けられた曲輪の内容を明らかにした。この曲輪は丘陵尾根部にあり、周囲から半ば独立して造り出されている。曲輪頂部は方形に造り出され、西・北・南の3辺には防御用の土塁が築かれていた。出土遺物から16世紀のものである \n\n[長岡京跡右京第994次・井ノ内遺跡 要約]\n周辺の調査では、弥生時代後期の集落を巡る環濠が確認されているが、今回検出した大溝の方向はその環濠に直交する位置関係にある。長岡京期から平安時代にかけての掘立柱建物跡・柵列が、推定西三坊大路の路面上で見つかった。この遺構群が長岡京期のものである確証はないが、大路を挟んだ両町を占有した大規模宅地である可能性も否定できない \n\n[椋ノ木遺跡第8次 要約]\n中世の遺構面では、火を受けた土器や焼け土、炭、鉄滓、フイゴの羽口、石鍋などが出土し、集落内で小規模ながら鍛冶作業を行われていたことが想定される。また、柱穴内に土師器皿20枚が埋納されており、何らかの儀礼が行われたと考えられる。そ縄文時代の遺構として、落ち込みのような浅い土坑や杭跡と考えられる小穴群を検出した \n\n
遺跡名 : 鞍岡山古墳群
都道府県 : 京都府
遺跡所在地 : 京都府相楽郡精華町下狛小字砂川
市町村コード : 26366
北緯(世界測地系) : 34.775277
東経(世界測地系) : 135.784166
主な時代 :
時代・遺跡種別 : 古墳
主な遺構|主な遺構 :
主な遺物|主な遺物 :
総覧URL : https://sitereports.nabunken.go.jp/25708
特記事項 : 調査の結果、自然地形