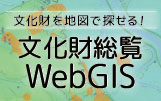総覧抄録ID : 130387
要約 : (筑後国府跡 第215次)\n本調査は、筑後国府Ⅱ期政庁に付随する国司館の南西コーナー部分の検出を目的とした重要遺跡遺構確認調査である。調査の結果、想定どおりに国司館南区画の南辺溝と西辺溝を検出し、国司館南区画の南西コーナー部を確認できた。このコーナー部は、互いの溝が接続しないことが判明し、掘り直しを含めた2時期存在することが確認できた。また、このコーナー部を検出したことにより、国司館南区画の南辺幅が、東西約70mであることが判明している。出土遺物は、緑釉陶器や灰釉陶器、越州窯系青磁、墨書土器など特筆すべきものも多い。\n(筑後国府跡 第217次)\n第217次調査は、筑後国府域の中央を東西に縦貫する推定官道の遺構確認調査である。従来の路線復元では、対象地において推定官道の路面幅が確認できることが予想された。調査では、予想どおりに道路遺構を検出することができ、路面幅が約11mであることも判明した。また、この道路遺構を掘り下げた結果、上下2面の存在が確認できた。1期目は、側溝を伴う幅約6.6mの道路遺構で、2期目は積土により構築している。側溝を伴わず、基底部には突き固めの痕跡も確認できた。敷設時期は8世紀代と想定されるが、詳細なじきは確定できなかった。また、廃絶時期は路面に含まれる遺物から10世紀代が想定される。\n(筑後国府跡 第221次)\n第212次調査の未調査部分を調査。直接道路遺構SF3980に関係する遺構は検出されず、Ⅱ期政庁期の土坑が検出されたのみであり、北側に隣接する第198次調査の成果からも、調査地周辺は同時期の建物群が散在するのみの状況であったと推定される。\n(筑後国府跡 第224次)\n本調査は、筑後国府Ⅰ期政庁の南側隣接地で実施した遺構確認調査である。対象地内において、Ⅰ期政庁の南辺築地外溝が検出されると予想された。しかし、南辺築地外溝推定地まで調査区を拡張することができず、弥生時代終末期の遺構を検出したに止まった。\n(筑後国分寺跡 第44次)\n調査地点は、従来の伽藍配置復元案によると南面回廊の推定線上にあたる。しかし、関連する遺構は検出できなかった。東西に並んで検出された方形掘形2基は、一辺の長さが1.65~1.95mを測り、最終的には南側へ柱を抜かれていた。また、掘形内や抜き跡からは瓦片が出土しており、創建時のものではないと思われる。この柱穴の性格については、掘立柱建物や幢竿支柱などが案として考えられるが、特定するに至っていない。その他にも、溝状の地形痕跡や大形土坑などもあり、周辺地域での今後の調査が期待される。\n(筑後国分寺跡 第45次)\n塔基壇南裾の検出を目的とした調査である。結果、基壇裾部は近現代の溝によって破壊されていたものの、土層観察から、基壇の南北幅は約19m前後と推定することができた。これは、従来の推定値よりも1m前後南側へ拡大したことになる。また、版築基壇は現地表下約1.1mで基底部に達し、そこから厚さ3~10cmずつ互層状に積土を施して形成している様子が観察される。\n
遺跡名 : 筑後国分寺跡 第44次
都道府県 : 福岡県
遺跡所在地 : 久留米市国分町字政所733-1外
市町村コード : 40203
北緯(世界測地系) : 33.294722
東経(世界測地系) : 130.537222
主な時代 : 奈良|平安
時代・遺跡種別 : 社寺
主な遺構|主な遺構 : 方形掘形 2基|大形土坑 1基|地形 1基
主な遺物|主な遺物 : 土師器|須恵器|古瓦|黒色土器
総覧URL : https://sitereports.nabunken.go.jp/65211
特記事項 : 従来の伽藍配置復元案では、南面回廊の推定線上に位置する。回廊関連遺構は検出できなかったが、一辺の長さが2m近い大形の方形掘形2基を発見した。